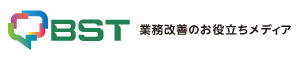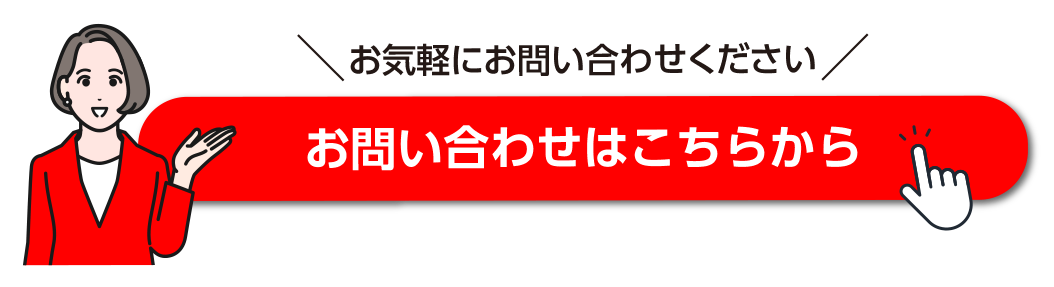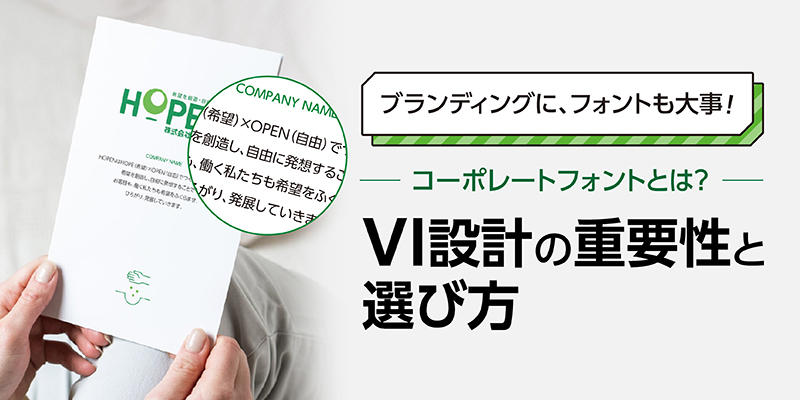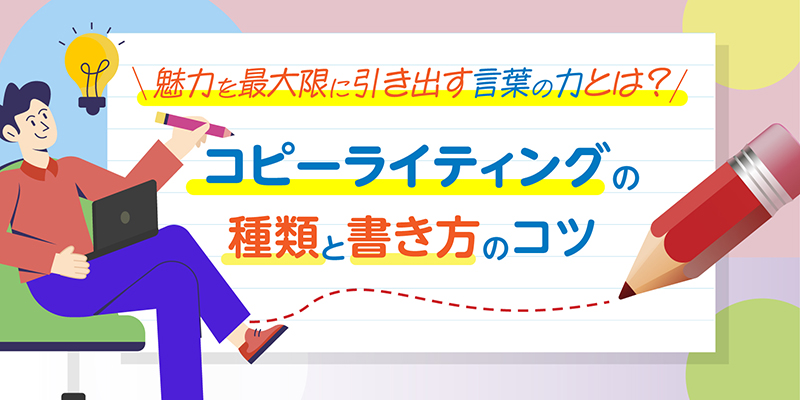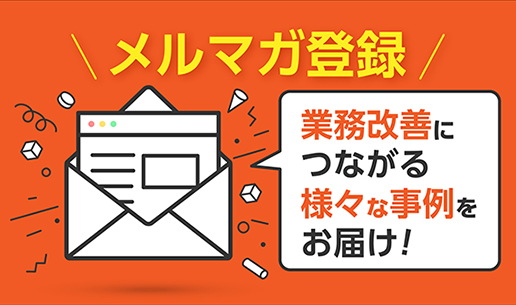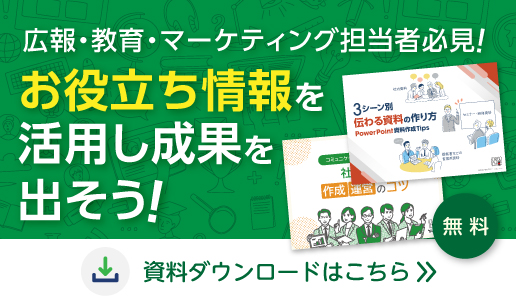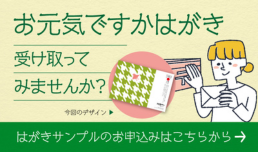.png)
創業50年以上の企画製造会社が提案する「気軽に取り組むSDGs!」Vol.4
今回のVol.4では、食品ロス削減月間でもあることから、奈良県の老舗用紙メーカーである株式会社ぺーパル社が、フードロスをなくす取組みの第1弾として開発した、廃棄されるお米でつくられる紙「kome-kami」をご紹介させていただきます。
「kome-kami」は、「捨てられるお米が紙になる?」そんな驚きのプロジェクトが、奈良の老舗用紙メーカーによって誕生しました。
今回は、食品ロス削減とSDGsを掛け合わせた紙素材『kome-kami』は、どんな紙なのか、なぜフードロス削減につながるのか、どう活用できるのかについて、わかりやすく解説します。
この記事は、ホープン(旧社名:プリントボーイ)が創業より続けているアナログコミュニケーション、“お元気ですかはがき”のテーマと連動した記事となります。
記事で紹介しました環境に優しい用紙が気になる方は、 “お元気ですかはがき”としてご希望のお客様のお手元にお届けいたします。記事とあわせて是非ご覧ください。
(kome-kamiの紙での発送をご希望の場合は、お問い合わせ内容の入力欄に「kome-kami希望」と記載いただけましたら幸いです。)
お元気ですかはがき 隔月受取希望のお客様はこちらから

- 食品メーカーの経営者の方
- 企業・大学の総務や広報の方
- 社内SDGs推進プロジェクトメンバーの方
- セミナー、研修企業の運営担当の方

- フードロスをなくす取り組み、循環型社会と事業を結びつけるヒントが得られる
- 新しい用紙「コメカミ」の情報が得られる
- パーパスブランディングのヒントが得られる
▼ 気軽に取り組むSDGs!バックナンバー記事
- 人にも環境にも優しい、バガスペーパーとは?|印刷会社が提案するSDGsの取り組み Vol.1
- プラスチックでも紙でもない、新素材 LIMEX(ライメックス)|印刷会社が提案するSDGsの取り組み Vol.2
- フェアトレードの輪がつくる紙。アフリカ生まれのバナナペーパーって?|印刷会社が提案するSDGsの取り組み Vol.3
◆目次
1.食品のムダ、そのままで大丈夫?
毎日、まだ食べられるのに捨てられている食品が日本国内で612万トンも発生していることをご存知ですか?
「フードロス」「食品ロス」という言葉は、今では一般的になりましたが、食品ロスとは、本来食べられるものにも関わらず、捨てられてしまう食品のことです。
家庭の食べ残しやスーパーの売れ残りに加え、企業や自治体が備蓄する災害用食品の多くも消費期限切れで廃棄されており、見えないところで大量の食品がムダになっています。
なぜフードロスは問題なのか?
この大量の食品廃棄は、単なる「もったいない」問題ではありません。
フードロスを削減する取り組みは、以下の点でも有効です。
-
焼却時にCO2を排出し、環境負荷が大きい
-
処理費用が膨大になり、経済的負担も増大
-
世界人口の増加により、食料不足が深刻化
こうした課題に対する新たな解決策として生まれたのが、『kome-kami』です。
2.廃棄されるお米が生まれ変わる!新しい発想の紙「kome-kami」とは

*画像(株)ペーパル社ご提供
「kome-kami」とは、廃棄予定のお米をアップサイクルして作られた、環境に優しい新しい紙素材です。
この取り組みは、奈良県の老舗用紙メーカー・ペーパル社が開発し、食品のムダ削減と持続可能な社会の実現を目指す「ロスチェンジプロジェクト」の第一弾として誕生しました。
なぜお米を紙に?
特に、備蓄用の非常食米*や、メーカーで発生する破砕米、家庭や流通段階で消費されずに廃棄されるお米を原料とし、
-
環境負荷を減らす
-
食品廃棄量を削減する
-
売上の1%をフードバンクに寄付する
という仕組みで、単なるリサイクルではなく新しい付加価値を生み出しています。
kome-kamiの特長
kome-kamiは、以下の特長があります。
-
廃棄予定のお米を有効活用!
食品のムダ削減+循環型社会を実現する取り組みに繋がります -
お米ならではの、しっとりした質感
通常の紙よりなめらかで優しい手触りで、印刷適性も抜群
紙そのもののもつ豊かな風合いにお米の質感が加わり、触ってみるとラフでありつつもしっとりした表面です。 - 色は艷やかなお米を思わせる、ナチュラルな白さ
-
売上の1%をフードバンクに寄付する
使うだけで社会貢献につながります -
非常食米のほか、メーカーで発生する破砕米や、家庭・流通で使われなくなったお米も使用
アップサイクルによって、kome-kamiは環境への負荷を減らしつつ高品質な紙として活用可能です。
kome-kamiの循環型プロセスとSDGsへの貢献
廃棄される予定だったお米を紙にアップサイクルする「kome-kami」の循環型システムを示したものです。以下にそれぞれの項目についてご紹介いたします。

*画像(株)ペーパル社ご提供
-
非食用米の活用
協賛団体から提供された食べられなくなったお米を原料として活用します -
保管・粉砕
廃棄予定のお米を適切に保管し、紙の原料として使用できるよう粉砕します - 紙の製造
粉砕したお米を紙の原料に混ぜ、独特の風合いと質感を持つkome-kamiが製造されます -
紙製品の活用
ノートや封筒、名刺などの文房具や印刷物として利用され、消費者の手に届きます -
古紙回収・リサイクル
役目を終えた紙は回収され、新たな紙の原料として再利用されます。 - 紙の製造
粉砕したお米を紙の原料に混ぜ、独特の風合いと質感を持つkome-kamiが製造されます -
売上の1%をフードバンクに寄付
kome-kamiの売上の一部は、フードバンクへ寄付され、食品支援活動に役立てられます
アップサイクルによって、kome-kamiは環境への負荷を減らしつつ高品質な紙として活用可能です。
この取り組みにより、食品ロスの削減、資源の有効活用、環境負荷の低減を実現し、持続可能な社会づくりに貢献します。
kome-kamiは、まさにSDGsの「つくる責任 つかう責任」(目標12)に寄与するエコ素材といえます。
SDGsに関して気になる方は以下の記事をご覧ください。
▼SDGsに関する記事はこちらをご覧ください
SDGs(エスディージーズ)の取り組みは必要?|企業にもたらすメリットを解説!
3.こんなシーンで活躍!kome-kamiの使い方
kome-kamiは以下のようなシーンでご利用いただけます。販促やDMなどで様々な場面でご活用いただけます。-
企業のSDGs活動として
名刺や封筒、広報誌に活用することで、企業の環境意識のアピールを事業活動に関連する形でフードロス削減に取り組むことができる -
食品業界(食品メーカー)・酒造業界の販促ツールとして
DMやパッケージに活用することでブランド価値向上することにもつながります - 自治体・学校の広報誌に
環境教育の一環として導入し、持続可能な社会づくりに貢献できます
また、SDGsに関心が高いZ世代にも人気で、環境意識の高い企業にて積極的に採用していますので、ご検討頂くのはいかがでしょうか。
4.まとめ
今回は、廃棄されるお米を紙として再活用する「kome-kami」の取り組みをご紹介しました。kome-kamiは、食品廃棄を減らすだけでなく、その収益の一部をフードバンクへ寄付することで、食の支援にもつながる社会貢献型のエコ素材です。
フードロスの問題は、決して遠い話ではなく、私たちの暮らしにも直結する課題です。日常的に使う紙を環境に優しいものに変えるだけで、持続可能な社会づくりに貢献できますので紙から取り入れてみるのは、いかがでしょうか。
お元気ですかはがきのお申込みの際には、お問い合わせ内容にkome-kami希望と記載いただけましたら幸いです。
ホープン(旧社名:プリントボーイ)では、名刺や封筒、DMなどの印刷物から、御社に合う用紙のご提案まで幅広くご提案が可能です。
今回ご紹介しました「kome-kami」を取り入れることで、企業のSDGs活動やエシカルなブランド価値向上にもつながりますので、
「気軽に取り組めるSDGs」として、まずは紙から取り入れてみてはいかがでしょうか。
また、ブランディングのご支援として、お取り組みを訴求するブランドムービーなどの動画制作も可能です。
様々なコンテンツ制作でサポートできますのでお気軽にご相談ください。
▼ この記事を読んだ方はこちらの記事も読んでいます
- SDGs(エスディージーズ)の取り組みは必要?|中小企業にもたらすメリットを解説!
- プラスチックでも紙でもない、新素材。用途広がるLIMEX(ライメックス)。 創業50年の印刷会社が提案する「気軽に取り組むSDGs!」Vol.2
- 捨てられていた人参(ニンジン)の皮を活用したアップサイクル用紙「vegi-kami にんじん」
- クラフトビール(Craft Beer)を味わい尽くす「クラフトビールカード」
- フードロス(食品ロス)をなくす挑戦!食べられなくなったお米が紙に生まれ変わる、「kome-kami(コメカミ)」
▼ 参考サイト
- 食品ロスの現状を知る|農林水産省
- kome-kami |株式会社ペーパル
- 食べられなくなった「お米」を活用した紙の新素材「kome-kami」|PR TIMES
当社はFSC® CoC認証を取得しています。当社のライセンス番号はFSC-C133621です。
We are certified to the FSC® CoC standard. Our license code is FSC-C133621.