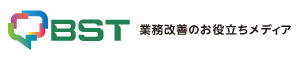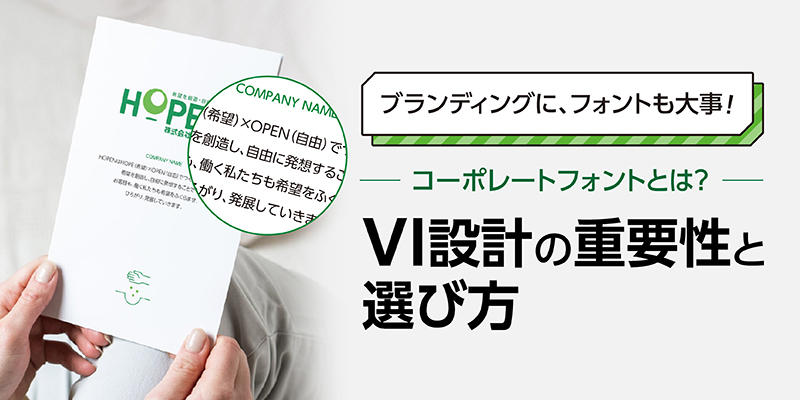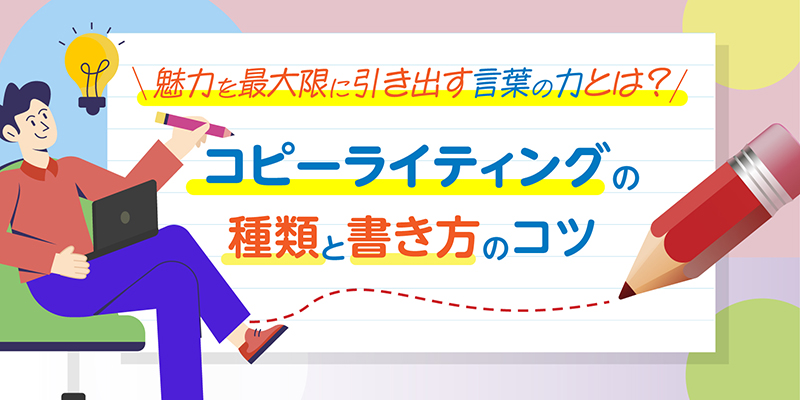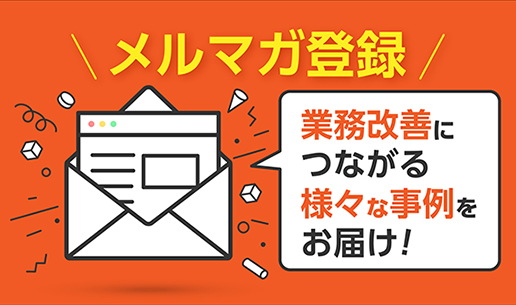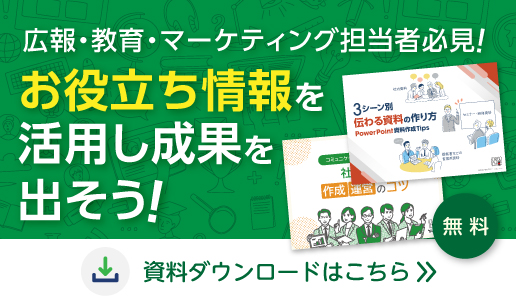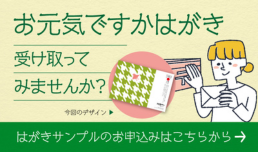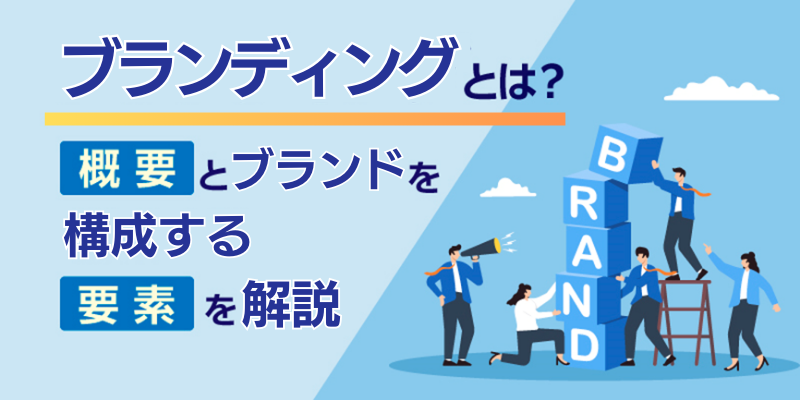
皆様は「ブランディング」に関するお取り組みはどのようなことをされていますでしょうか。情報が溢れ、選択肢が増えた現代では、企業がお客様に選ばれるには「ブランディング」が重要です。
本記事では、ブランディングの基本から構成する10の構成要素、さらには効果的に推進するための考え方などをわかりやすく解説します。
◆目次
1.ブランディングとは?マーケティングとの違い

ブランディングとは、企業や商品・サービスがもつ独自の価値や世界観を、顧客に認知・共感してもらうための一連の取り組みのことです。
マーケティングが「売れる仕組みをつくる」ものである一方、ブランディングは「選ばれる理由をつくる」ものと言い換えることができます。
競争が激しい現代では、単なる商品スペックや価格ではなく、顧客の感情に訴える価値づけがカギとなります。
そのために不可欠なのが、ブランディングです。
ブランディングが推進され、世の中に広く認知されて信頼性や共感力を備えることができれば、自社の製品・サービスの価値がさらに向上し、他社との差別化に成功できるといえます。
そのため、供給過多な時代においては、「マーケティング戦略」の一つとして早めにブランディングを行い推進することが大切です。
また、ブランディングを効果的に進めるためには、「どんな人に、どのような価値を届けるのか」を明確にすることも重要になります。そこでポイントになるのが、次にご紹介します「ペルソナ設定」 です。
2.ブランディングにおけるペルソナ設定の重要性
ブランディングを推進させるためには、まず 「誰に届けるのか」 を明確にすることが不可欠です。
これを具体的に設定するのが「ペルソナ設定」です。
ペルソナが重要な理由とは?
ペルソナを設定することで、ブランディングの方向性が明確になり、ターゲットに響くメッセージを発信できるようになります。
例えば、以下のような項目を決めると、理想的な顧客像が浮かび上がります。
・年齢・性別(例:20代女性、30代ビジネスマン など)
・職業・年収(例:会社員、フリーランス、年収500万円 など)
・ライフスタイル(例:趣味、休日の過ごし方 など)
・価値観・好み(例:オーガニック志向、ミニマリスト など)
・SNSやWebの利用状況(例:Instagramを頻繁に利用、YouTubeで情報収集 など)
ペルソナを明確にすることで、ブランドのコンセプト、デザイン、キャッチコピーなどの方向性がぶれずに、一貫性を持たせることができます。
そのため、誰に届けたいのかを明確にすることが大切です。
ペルソナに関しては以下に詳しくまとめております。ご興味ある方は以下の記事もぜひご覧ください。
▼「ペルソナ」に関する記事はこちら
【具体例つき!】ビジネスにおける「ペルソナ」とは?意味や設定方法を知り、マーケティングの精度を高めよう
3.ブランディングを構成する10の要素
より強固なブランディングをするために、まずはブランドを構成する要素分解を行っていくのがおすすめです。
以下に、ブランディングに不可欠な構成要素を10つご紹介します。ブランディング施策として取り組まれていない要素があればぜひご検討ください。
3-1.ブランド名を決める
ブランド名は、企業や商品・サービスの第一印象を決定づける極めて重要な要素です。顧客が最初に接する言葉であり、認知や記憶に深く関わる「ブランドの顔」ともいえる存在です。
その企業の理念やビジョン、目標などを基準にしながら、企業を代表するネーミングが発想できれば、顧客の共感や信頼を得ることができます。
ブランド名を決める際には、次のような視点がポイントです。
▼ ブランド名を決める際の4つのポイント
-
覚えやすさ(短くて発音しやすい)
-
独自性(他社と差別化されている)
-
意味やストーリー性(理念や提供価値が反映されている)
-
視認性・検索性(検索エンジンで見つけやすい、ドメイン取得しやすい)
▼ 他社事例はこちら
-
無印良品:その名の通り「ブランドを付けずに品質を追求する」姿勢を明確に表現しています。
-
ユニクロ(UNIQLO):"Unique Clothing"からの造語。グローバル展開でも可能なネーミングです。
-
スノーピーク(Snow Peak):創業者が登山好きだったことから、自然志向・アウトドアのイメージが一目で伝わるネーミングです。
また、ブランド名を決める前に行うべきステップとして、以下も重要なポイントです。
▼ブランド名を決める際に気を付けたいポイント
-
ターゲット層の明確化(ペルソナ設計)
-
競合ブランドの調査
-
海外展開を考慮した発音や意味のチェック
-
ドメインや商標登録の可否確認
「名前」は、ブランドの物語のはじまりであり、ブランドの「顔」です。ブランド名を変えたら売上が大幅に変わったなど、影響も大きいともいわれますので市場調査や競合分析を行って決めていきましょう。
3-2.ブランドロゴ・ロゴマーク

ブランドロゴやロゴマークも、その企業や商品を象徴するイメージとして、ブランディングに欠かせない要素です。
ロゴは、ブランドの世界観や価値観を視覚的に伝える重要なシンボルです。一目見ただけで企業やサービスを想起させる「記号」としての役割を担い、信頼感や親近感、あるいは高級感などの印象を与えることができます。
ロゴデザインで重視すべきポイントは4つあります。
▼ ロゴデザインで重視すべき4つのポイント
-
視認性:小さなサイズでも見やすく判別しやすい
-
再現性:モノクロ・カラー問わず各媒体で崩れない
-
独自性:他社と混同されないユニークさ
-
メッセージ性:ブランドのコンセプトがにじむデザイン
▼ ブランド名を決める際の4つのポイント
-
Appleのリンゴマーク:シンプルでミニマルなデザインは、洗練された技術とユーザー体験を象徴しています。
-
NIKEのスウッシュ:スピード感と力強さを一筆のラインで表現し、スポーツブランドとしてのエネルギーを体現しています。
-
Starbucksのセイレーン:神話の海の精をモチーフに、非日常的で豊かな時間を提供するブランドイメージを構築しています。
また、ロゴは単体で完結するものではなく、他のビジュアル要素(カラー・書体・レイアウト)との組み合わせによって、ブランド全体の印象を左右します。ロゴは単なる飾りではなく、「誰にどう見られたいか」を端的に伝えるブランディングの核になります。
ブランドの立ち上げや刷新を検討している場合は、ロゴデザインを含むビジュアル・アイデンティティ(VI)設計も含めて決めていくことが重要です。
ロゴは視覚的にブランドを認識させるシンボルになりますので、与えたいブランドイメージに合うデザインになるようにどのようなデザインが良いかなど決めていきましょう。
ホープンでは、ロゴデザインもご提案が可能ですのでお気軽にご相談ください。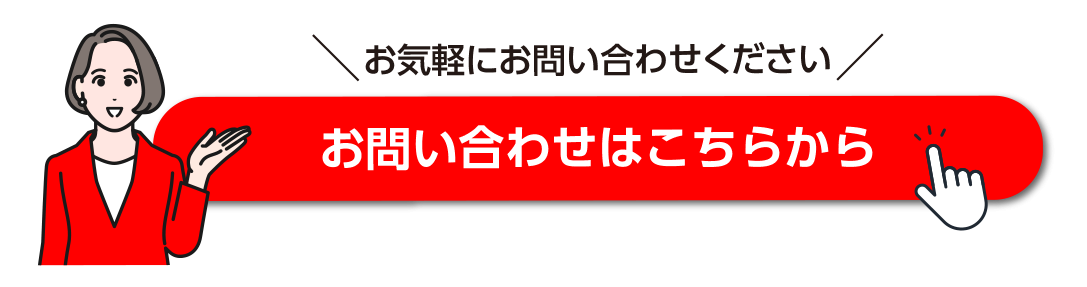
3-3.心に残るキャッチコピー
キャッチコピーは、ブランドの想いやコンセプトを、短く端的に伝えるための「言葉のデザイン」です。広告、Webサイト、パッケージ、SNSなどあらゆる場面で目にするこの一文が、消費者に与える印象を大きく左右します。
優れたキャッチコピーは、ブランドの世界観や強みを簡潔に伝えると同時に、見る人の心に残り、共感や好意を生み出しますので、ブランドを表現するのに適しているキャッチコピーを決めていきましょう。
キャッチコピーについては、以下の記事で詳細をご紹介していますので、ぜひ以下の記事もご覧ください。
▼キャッチコピーに関する記事はこちら
事例も紹介!心に刺さる魅力的なキャッチコピーの特徴とは?
3-4.ブランドカラーを決める
ブランドカラーは、企業や商品の印象を瞬時に伝える「視覚的なキャッチコピー」です。
ブランドの理念やビジョンを色で表現することで、顧客に強い印象を与え、共感や信頼を生み出すことができます。
また、ブランドカラーは企業のアイデンティティを象徴する重要な要素ですが、選ぶ色によって企業のメッセージや雰囲気が大きく変わります。
色は、実は色(カラー)毎に、心理的効果がありますので、ブランドカラーを決める際には色が持つ心理的効果を活用することも可能です。
以下の記事では、色ごとの与える効果と、それぞれのブランドカラーを使用している事例などをご紹介していますので、色についてご興味ある方はぜひご覧ください。
▼カラーブランディングに関する詳細はこちらをご覧ください。
「カラーブランディング」とは?ブランドカラーが与える色の効果を解説!
3-5.デザイン

デザインは、ブランドの印象や世界観を「見た目」で伝えるための重要な要素です。商品パッケージ、広告、名刺、店頭ディスプレイなど、あらゆる場面で統一されたビジュアルが使用されていることで、ブランドの認知度と信頼感が高まります。形・色などにオリジナル要素を入れるなど配慮することで、自社商品と認識してもらいやすくなるため、ぜひデザイン面も大事にしましょう。
ただし、オリジナル要素を入れるとはいえ、デザインがあまり奇抜すぎると、顧客の評価が得られない場合もあります。
そのため、どの属性をターゲットにするのかなどの検討や、多くの人々に受け入れられる広義な考え方も踏まえ、競合分析など行いながら検討していくことが大切です。
3-6.キャラクターによる共感の獲得
オリジナルキャラクターは、ブランドに対する親しみや信頼を自然と育む力を持った、感情的な接点を生み出すツールの一つです。
特にBtoC領域では、企業や商品に直接的な「顔」を与えることで親近感を与え、顧客との距離感を縮めることができます。
キャラクターが浸透することで企業イメージがやわらかくなり、ファン化やSNSでの拡散にもつながっています。
そのため、自治体や銀行、医療機関など堅い印象のある業界でも、キャラクター導入により親しみやすさを創出する成功例が多く見られます。
キャラクターは、単なる“マスコット”ではなく、ブランドのメッセージや世界観を代弁する存在です。
広告やイベント、ノベルティ、SNSなど多様なタッチポイントで一貫して活用することで、ブランドとの継続的な関係づくりを支援することができますのでブランドキャラクターも取り入れてみてはいかがでしょうか。
以下の記事では、ホープンの事業の一つである「雑貨店」のキャラクターとして推進しています、「ゆい吉」の活用例を交えながら、キャラクターブランディングについてご紹介しています。
キャラクターブランディングにご興味がありましたら、以下の記事もご覧ください。
▼キャラクターブランディングについての記事はこちら
キャラクターブランディングとは?「ゆい吉」の取り組みを例に解説
3-7.匂いや香り
訴求したい商品などによっては、匂いに気を遣ってブランディングをするケースもあります。
嗅覚に訴えることで、特定の記憶を呼び起こす効果があると実証され、それをうまく活用したブランディング手法です。
例えば、空港は非日常的な高揚感を持たせてくれますが、ANAなどの航空会社では、ラウンジエントランスに独自の香りを選定して利用する戦略をとっているといわれています。
また、他にもTHE BODY SHOPの店頭の前を通り過ぎる時も、甘い独特な香りがしたりブランド推進にあたり匂いや香りで演出することも戦略の一つです。
3-8.ブランドサイトの構築
ブランドイメージやコンセプトが明確になったら、それを具体的に伝える手段として、公式Webサイトの構築は欠かせません。Webサイトは「企業の顔」であり、第一印象を決定づける重要な接点です。サービス紹介、採用情報、ニュースや事例紹介など、顧客との信頼を築くための情報を一元的に発信できます。
また、Webサイトを構築する際には、次のような点を意識すると良いとされています。
▼ Webサイトを構築する際の3つのポイント
-
ブランド名や関連キーワードを含むドメインの取得
-
ブランドカラー・ロゴ・フォントとの統一感あるデザイン
-
定期的な更新による活発さの演出
さらに、検索エンジンでの露出を高めるためには、SEO対策も大切です。ターゲットユーザーが検索するキーワードを調査し、適切にコンテンツへ反映することで、より多くの訪問者を獲得することができます。そのためには、自社メディアやブログの運用も、ブランディングの長期的推進には有効ですのでご検討されてみてはいかがでしょうか。
加えて見落とされがちですが、「ウェブアクセシビリティ」の配慮も現代のブランディングにおいて欠かせない要素の一つです。色覚多様性への対応、文字サイズの調整、読み上げソフトへの対応など、誰もが使いやすいWebサイトを目指すことが「企業の姿勢」そのものとして評価される時代ですので、ウェブアクセシビリティも意識して設計するようにしましょう。
ウェブアクセシビリティについて詳細を知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。
▼「ウェブアクセシビリティ」に関する記事はこちら
ウェブアクセシビリティとは?対応すべき4つの理由
3-9.フォントの統一によるブランドイメージの推進
ブランドの印象は、色やロゴだけでなく「文字」からも大きな影響を受けます。特にWebサイトやパンフレット、広告、プレゼン資料など、文字情報が中心となるタッチポイントでは、使用するフォントが企業らしさを視覚的に伝える重要な要素となります。
たとえば、堅実さや信頼感を伝えたいなら明朝体、モダンで先進的な印象を与えたいならサンセリフ体など、フォントの選び方ひとつでブランドの空気感が変わります。さらに社内の資料や営業ツールなどにも統一されたフォントを使用することで、社内外の一貫したブランドイメージ形成が可能になります。
「なんとなく使いやすいから」「PCに入っているから」ではなく、戦略的に選定されたフォントが、見えない部分でブランド価値を底上げしてくれるため、ブランド設計の際にはより伝わるフォントを選定することがおすすめです。
以下の記事は、「コーポレートフォント」に関するVI設計についてフォントの選び方をまとめておりますが、コーポレートフォント以外でもお役に立てる情報になっております。
ブランドイメージを伝えるためにどのようなフォントを選ぶと良いか、気になる方は以下の記事もぜひご覧ください。
▼フォントの選び方に関する記事はこちら
コーポレートフォントの選び方とは?VI設計の重要性と選び方
3-10.VI(ビジュアル・アイデンティティ)の設計

「VI(Visual Identity)」とは、ブランドの視覚的要素を体系的に整理・統一する設計手法です。具体的には、ロゴ、ブランドカラー、フォント、アイコン、写真のトーン、レイアウトルールなどが含まれます。これらをガイドラインとして明文化することで、どのタッチポイントでも「その企業らしさ」がブレずに表現できるようになります。
たとえば、複数の部署がチラシやプレゼン資料を作成する際、VIが設計されていればバラバラな印象になることなく、ブランドとしての一貫性が保たれます。さらに、外注先やパートナー企業と制作を進める際も、ガイドラインを共有することでスムーズにクオリティを統一できます。
近年、SNS運用やイベント、ノベルティ、ECサイトなど、ブランドの露出機会が多様化していますが、それらの場面で「見た目の統一」がされていないと、企業の印象や信頼感に大きく影響することもあります。だからこそ、VI設計はブランディングにおいて“根幹”となる存在となるため大切ですので、VI設計も併せて行うようにしましょう。
4.まとめ

今回は、ブランディングのご紹介として概要と構成する10つの要素を中心にご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。ブランディングの推進は中長期的な取り組みが必要でして、すぐに結果が出るとは限りませんが大切な取り組みです。ブランディングには様々な要素が必要ですが、できるところから取り組んでいきましょう。
ホープン(旧社名:プリントボーイ)では、「ブランディング」推進のためのコンテンツ制作が可能です。ブランドイメージを伝えるパンフレット制作や、ブランドムービーの制作や、コンセプトムービーの制作、その他ブランドブックの制作など、ブランディング推進に関する様々なご支援が可能ですので、お気軽にご相談ください。